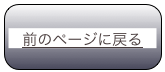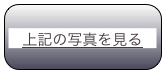大変だー!
味噌にカビが発生している!
大変だー!
味噌にカビが発生している!



平成21年8月16日、カビを取り除きました。
記録を取りましたので、参考にして下さい。


右は別の樽です。
カビは点々とほんの少し。取り除いてから、切って見ました。 写真では分かりにくいですが、 中より周囲部の熟成が進んでいます。
全体が混ざる様におにぎりにして、樽の中の新しいビニールにに詰めました。
ヨーロッパのチーズ見たいですね。







樽からそーっと、味噌を取り出しました。
樽からそーっとビニールごと引っ張りだして、新聞紙の上に慎重に置きました。カビが混ざらないように、注意しながら。。。
夏は、前半温度が上がらず、ここ2週間しか夏日がありません。例年より仕上がりが遅いかなと思いつつ、物置から味噌を引っ張りだし、2斗樽4樽中、2樽に青、黒、白のカビを発見してしまいました。
ビニールを丁寧に切り取りました。
カビの部分が横にもまわっていましたので、ビニールの口から取り除くのを諦め、ビニールの周囲をカッターやはさみで切り取りました。切り取ったビニールは、菌が着いているので、速やかに、ゴミ袋に隔離しました。
包丁でゆっくり削ぎ取ります。
もったいないけど、少し多めにそぎ落としています。包丁にカビが直接着かないように、丁寧に。刃にカビが着いたら、思い切って、洗い直して、また削ぎ落とします。
横の隙間にもありました。包丁やスプーン、ナイフを使いました。ボールの中は捨てる味噌がいっぱいになって来ました。もったいないけど、諦めます。
きれいな肌になりました。
もし全体にカビが廻っていたら、表面をすべて取り除きます。底にもある場合は、上部と横面をきれいにして、きれいな部分を包丁で切り取って分けていくと楽です。工夫して下さい。
中の隙間にもカビがあるか確認しました。
表面にカビがあったので、中に隙間があったらカビがある可能性もあると聞きましたので、おにぎり一つ分取り、上、下、右、左と順番に崩しながら全体が混ざる様に、きれいな漬け物袋に入れました。二斗樽と少し多めに仕込みましたので念の為。
もう食べる様なので。
少し早いかなと感じつつ、味噌になっていたので、天地返しのつもりで、 新しいビニール袋に入れ全体を揉んで混ぜ合わせました。新鮮な空気も入りました麹菌も最後の熟成をがんばってくれます。いいにおいです。 もうすぐ食べ始めます。 冷蔵庫に入れました。
熟成がまだなら、隙間なく元の様に樽に仕込み、熟成を待ちます。天地返し後は、カビの監視をしっかりして下さい。樽に仕込むときは消毒を行って下さい。
ちょっとがんばって読んでみて!
折角なので、きれいになったら、少し味見をして見ましょう。部分によっては、特に塩辛く感じます。味噌ってしょっぱいものですね。熟成が進むと「塩なれ」と言って、塩辛さがマイルドになっていきます。
当方では、慎重にカビを取り除いています。その分、ロスも多くなりもったいない位です。
因に、ひとに食べてもらう場合は必ず加熱をしています。
半分冗談のつもりですが、お毒味のつもりで、畑のきゅうりを、生の味噌で十分に味わってからにしてます。
菌が味噌を作り出します。
味噌は麹菌やいろんな酵母菌が、大豆を分解して酵素を分泌し、風味やうま味を作り出します。これらもカビと言えます。
問題は毒素を持つ、又は作り、食品をまずくする腐敗菌類が食品に適さなくしてしまいます。仕込みのとき、「空気を抜いて。。。」と、覚えていますか、悪い菌の多くは、好気性の菌(酸素がたくさんい必要)なので、空気を抜くと発生し難いからです。その為、外側を除くと中は食べられるのです。ただし、中も嫌な匂い、味噌とは思えない色だったら注意が必要です。まずそうに感じたら、要注意。手作り味噌は風味も、うま味も、絶対に美味しいです。人間の感覚を信じましょう。
因に、うま味を作る麹菌や酵母菌は嫌気性(酸素が微量必要)です。
カビ自体は加熱するとほとんどの菌自体は死滅しますが、胞子や毒素が残ります。発生源にもなります。汚染された部分は、きれいに取り除きましょう。
おいしい味噌まで、あと一歩!!
ご自宅の味噌の出来映えを、成功談、失敗談、不安、質問を送って下さい。写真を貼付出来ればお願いします。来年の為に、経験を共有していきましょう。
katsuraoka@mbr.nifty.com 件名に「味噌講習」を入れて下さい。
以下の通り、手順を紹介します。